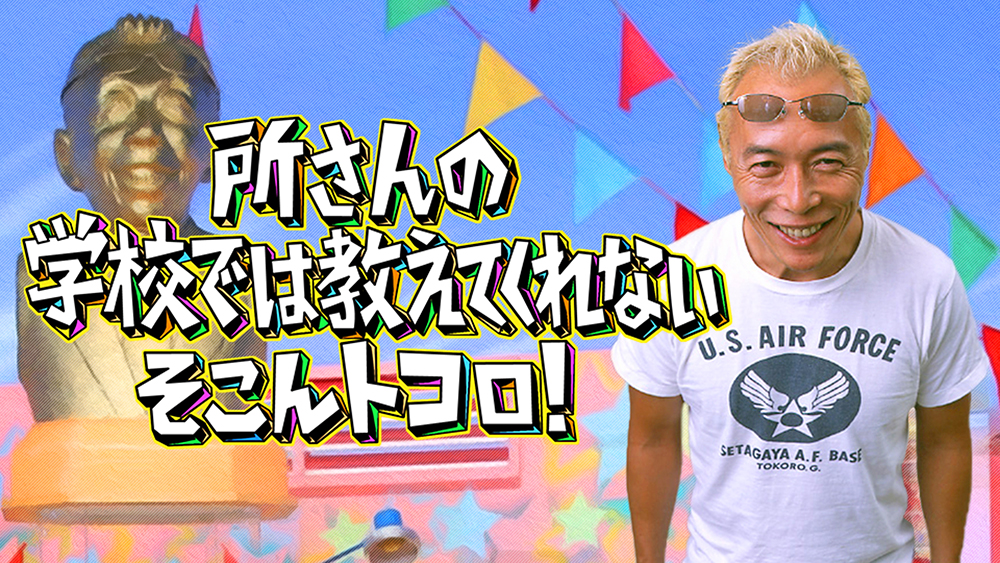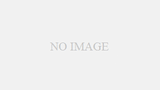『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!』 テレ東 (金) 21:00~
公式HP:http://www.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/
出演者:所ジョージ、東貴博、清水ミチコ、湯浅卓、山口もえ、大橋未歩(テレビ東京アナウンサー)
●抜き打ちテスト「野菜が完熟するとどうなる?」
○答え 甘味が増す
では、元々苦味のある野菜はどうなるのだろうか?
①「シシトウ」
滅多にお目にかかれないという「完熟シシトウ」が奈良県の「とぐちファーム」にあった。
通常は緑色で出荷されるシシトウだが、完熟すると赤くなり、さらに身も大きく成長する。
この完熟シシトウは作るのが大変難しく、赤く熟す前に腐ってしまうこともあるという。
完熟シシトウは、実に手に入りにくい貴重な野菜なのだ。
その糖度を測ってみると「10.3%(普通のシシトウが4.0%)」と、イチゴと同じ位の甘さだった。
②「ゴーヤ」
黄色く熟した果肉の中から出てきたのは、真っ赤になったツヤのある種。
普通のゴーヤは身が詰まってるのに対し、完熟ゴーヤは中に空洞がある。
黄色の果肉には苦味がなく、赤く熟した種は甘い。
種の糖度を測ってみると6.9%。ミカンと同じ位の甘さだった。

つまり、野菜の中には完熟すると果物のように甘くなるモノもあるということがわかった。
ちなみに、元々糖分が少ない野菜や葉っぱものは、熟しても果物のように甘くならないとのこと。
●『日本の島々を探検!島ダス』
○島ダスFile No.22「神津島(こうづしま)」
東京都にある離島・神津島。
伊豆諸島のほぼ中間に位置する島である。
この島にはほとんど平坦な地がなく、島の中央には「新日本の百名山」にも数えられている天上山がそびえ立つ。
島の人口は約2000人。主な産業は漁業と観光業である。
神津島の名前の由来は…
その昔、この天上山の頂に神様が集まって伊豆の島々を作る相談をしたという言い伝えがある。そのため、昔は「神集島」と書いたそうだ。
実は、この天上山は水の浸透性が高い火山岩と砂で出来ており、そのため雨水を吸収し常に大量の地下水を貯め込んでいるのだ。
おかげで島の人たちは昔から水に困ったことはないという。
島のいたるところから綺麗な水が湧き出し、生活に必要な水全てが天上山の地下水でまかなわれているのだ。
○テングサ
黒潮がぶつかり栄養分に富んだ海域にある神津島では、海の透明度も高いため十分な太陽光を受けて上質なテングサが育つという。
そのため神津島のテングサは最高級とされ一番の高値で取り引きされているのだ。
○きんちゃく漁
きんちゃく漁は10隻の船を使い、約50人の漁師たちで行われる大掛かりな漁。
周りの網をせばめていって魚を追い込み、最後にきんちゃく袋のように口を閉じて捕らえることからそう呼ばれている。
●『測れ!巨大物体X』
浄土宗・浄心寺(東京文京区)にある長さ2m5cm、重さ20kgの「巨大木魚ばい(ばち)」と、高さ1m40cm、奥行き2m、重さ500kgの巨大木魚。

そもそも、木魚はなぜ木の魚なのだろうか?
京都宇治市にある萬福寺には、中国から日本に最初に伝わった木魚の原型と言われるものが存在する。

木魚は元々、木を魚の形に彫ったものだったのだ。
実は、仏教では魚は目を閉じないために、眠らない生き物とされている。
そこには、魚のように寝る間を惜しんで精進せよとの意味が込められているのだ。
では何故木魚を叩くのだろうか。
答えは魚の口についているこの珠。

これは体から出た煩悩の現れなのだ。
つまり、木魚を叩くのは修行者の体から煩悩を取り除くため。
それが、いつしか、お経を読む際にも煩悩を取り除くために音のよく出る丸い木魚を叩くようになったという。
事実、今の木魚にもその名残りである、魚のうろこや煩悩を意味する珠などが彫られているのだ。
●『ミホの甘~い疑問』
○「『ういろう』はなぜ『ういろう』と呼ばれているの?」
「ういろう」のルーツは今から600年以上前に遡る。
中国の外交官で陳さんという人物が日本にやってきて、自らを陳外郎(ちんういろう)と名乗った。
陳外郎さんは医学に詳しかったため、日本で”せき”や”たん”に効く薬を作り出した。
それが評判となり、その薬に「ういろう」という名前が付いたのだ。
葛飾北斎の絵にも描かれている薬の外郎売。
「歌舞伎十八番」のセリフの中にも「昔ちんの国の唐人ういろうという人我が朝にきたり…」とある。
当時は有名な薬だったのだ。
では、なぜ薬だったはずの「ういろう」が和菓子の名前になったのか。
神奈川県小田原市にある「株式会社ういろう」。
こちらの創始者がそう名付けたらしい。
実は、外郎家では接客をする際に自家製の蒸し菓子を出して振舞っていたそう。
それが薬と対照的に甘くて美味しいと評判になり、和菓子にも「ういろう」という名前が付いて広まっていったのだ。
ちなみに、「ういろう」が名古屋名物といわれるようにになったわけは…
昭和39年に東海道新幹線が開通し、その時、名古屋のお土産として車内販売されたのが定着して名古屋名物となったのだ。
『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!』 8月26日