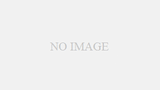『情報整理バラエティー ウソバスター!』 テレ朝 1月10日(土)19:00~20:54
公式HP:http://www.tv-asahi.co.jp/usobuster/
出演者:沢村一樹、北村総一郎、三船美佳、半田健人、里田まい、ゴリ(ガレッジセール)、宮崎美子
【内容】
テーマ毎に(一般的に)信じられてきた常識が4つ出てくる。
実はその中の3つがウソで、1つだけが信じてもいいホントの情報。
ゲストは力を合わせて3つのウソ常識を見抜き、ホントだと思う常識一つを選ぶ。
●テーマ『カラダ』
○「脂肪は20分以上運動しないと燃えない」(ウソ)
実は、体を動かすと脂肪はエネルギー源として常に燃やされているです。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
人間は運動した時、脂肪とともに体内にある糖もエネルギー源として使います。
運動し始めの頃はエネルギーとして取り出しやすい糖が多く使われ、運動を続ける中で徐々に脂肪を使う割合が増えていきます。
その脂肪を使う割合が糖より増えるのが約20分を過ぎた頃なのです。
これが「20分頃から脂肪が燃える」と勘違いされたという説があるのです。
○「年を取ると筋肉痛になるのが遅くなる」(ウソ)
そもそも、筋肉痛の原因は筋繊維が傷ついたことによって起こる炎症。
その発生が早いか遅いかは筋肉がどれほど損傷したかが左右するというのです。
運動で筋繊維が激しく損傷すると強い炎症が起こるため筋肉の炎症を早く感じます。
一方、筋肉の損傷が少なかった場合はジワジワと炎症が発生するため痛みを感じるのが遅くなるのです。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
人は年齢を重ねると若い頃のような激しい運動はしなくなります。
つまり、筋肉の損傷が少ない運動をして筋肉痛が遅れてくることが多いのですが、それを年を取ったせいだと思い込み、この俗説が広まったと考えられているのです。
○「骨折すると骨が太くなる」(ホント)
骨折するとその部分を修復しようと骨を作る成分がどんどん集まります。
この時、折れて弱くなった部分を頑丈にしようと以前より太く修復するのです。
○「暗い部屋でテレビを見ると視力が落ちる」(ウソ)
視力の良し悪しを決めるのは目のピント調節機能。
目は毛様体という筋肉が、レンズである水晶体の厚みを変え、ピントを合わせています。
この毛様体の動きが悪くなりピント調節が出来なくなるのが視力低下。
この機能の衰えに明るい暗いといった光の量は影響しないというのです。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
暗い部屋でテレビを見ると明るいところより光の刺激が強くなり目が疲れやすくなります。
その疲れ目の感覚が視力が悪くなったという思い込みを生んだと考えられるのです。
●テーマ『食べ物』
○「カキは加熱用より生食用の方が新鮮」(ウソ)
実は、生食用のカキは生で食べても大丈夫なよう、法律により細菌数の基準値が決められているのです。
そのため生食用のカキは出荷される前に工場へと運ばれ細菌を減らすため、紫外線で滅菌された綺麗な海水に一昼夜漬け込まれます。
そして細菌数を基準値以下にしてから出荷されるのです。
一方、加熱用は火を通せば細菌がなくなるため細菌数の基準が法律で定められていません。
そのため殺菌処理をせずに出荷してよいのです。
つまり、2つの違いは細菌数の基準値が決められているかどうかにあったのです。
加熱用は殺菌処理をしないため火を通しても旨味が多く残ります。
だから加熱料理には加熱用を使ったほうが美味しいのです。
○「ミカンは揉むと甘くなる」(ホント)
揉んだミカンは酸味が減って甘味が際立つようになるため甘く感じるようになります。
なぜ揉むと酸味が減るのかというと、ミカンは収穫後も生きているため呼吸をしていますが、実は揉まれるなどの刺激を与えられると呼吸が激しくなる性質があります。
この時、呼吸するエネルギーとして酸味の元であるクエン酸が消費されるのです。
その結果、酸っぱさが減り甘味が強くなったミカンになるというわけです。
ちなみに、ミカンは揉むとすぐ甘くなりますが時間が経つほどいいそうで、半日以上置くとより効果的なんだそうです。
○「ゴボウはアク抜きした方がよい」(ウソ)
アクの主な成分はシュウ酸。
レンコンやタケノコ、ほうれん草などにはシュウ酸がたっぷり含まれているため、アク抜きをした方が良いのですが、実はゴボウにはシュウ酸はほとんど入っていません。
だからアク抜きをする必要はないというのです。
ゴボウを酢水に漬けた際に出る茶色い汁は、実はポリフェノールだったのです。
つまりゴボウを酢水に漬けるとアクが抜けるのではなく、体に良い成分を抜いてしまうということだったのです。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
彩りを大事にする日本料理では見た目を美しくするためゴボウを酢水にくぐらせます。
酢が酸化を食い止めゴボウに変色を防ぐのですが、この色止めの作業がアクを抜いている作業と勘違いされ広まったという説があるのです。
○「酢飯は扇ぎながら混ぜるとよい」(ウソ)
扇ぎながら混ぜるとご飯はどんどん冷めていきます。
すると米粒の表面のデンプン質が固まっていき酢をブロックし、十分に酢が染み込まない酢飯になってしまうのです。
だからご飯がアツアツのうちに酢を混ぜ合わせた方が米粒の中までしっかり染み込むのです。
そして、混ぜ合わせた後に扇ぐことで水分が飛びベタつかない美味しい酢飯が出来上がるのです。
●『キングオブウソ常識!バスター3』
※番組が、今まで信じられていたのに実はウソという数々の情報を入手。
その集めたウソが世の中でどれほど信じられているのか100人にアンケートを実施。
ウソと知ってビックリした人数の多かったトップ3をランキングに。
○第3位「富士の樹海は方位磁石がきかない」(ウソ)
富士の樹海は地面が溶岩で覆われているため確かに磁力があります。
しかしそれは機械や器具に影響を及ぼすほどの磁力ではありません。
ですから方位磁石の正しい使い方である胸の高さで使えば正常に機能するのです。
ただし樹海の中には落雷などの影響で磁力が局地的に強くなっている場所があります。
そうした所では溶岩の上に直接方位磁石を置くと正常に作動しないことがあるのです。
そのためそのような磁力の強い溶岩の上にたまたま方位磁石を置いた人が、乱れた針を目にしたことから方位磁石が効かないという俗説が広まったと考えられているのです。
○第2位「日本一大きな砂丘は鳥取砂丘」(ウソ)
日本一大きな砂丘は青森県下北半島にある猿ヶ森砂丘だったのです。
実は猿ヶ森砂丘は防衛省の所有地。
弾薬の試験や射撃実験を行う試験場で一般人は立ち入り禁止となっています。
○第1位「虫は明るい所に集まってくる」(ウソ)
人間は紫外線を目で捉えることは出来ませんが虫の多くは紫外線をはっきり見ることが出来るのです。
つまり蛾やハエなどの虫は暗闇の中でも紫外線がよく見えるため、そこへ向かってしまうと考えられているのです。
●テーマ『睡眠』
○「寝つきが悪い時は羊の数を数えるとよい」(ホント)
人が眠りにつく時は脳の活動が低下します。
しかし、考え事をすると脳が活発化するため眠りづらい状態になります。
そこで、羊を数えるという単純な作業を繰り返すと考え事をしなくなるため脳の活動が低下していき眠りやすくなるのです。
○「お酒を飲むとぐっすり眠れる」(ウソ)
体に入ったアルコールは肝臓で分解されるとアセトアルデヒドという物質になります。
アセトアルデヒドは体や脳を刺激して活動的にする物質。
そのため寝ている間も脳が休まらず疲れがとれない睡眠になりやすいのです。
ちなみに睡眠の邪魔にならないようにするためにはお酒は寝る3時間前までにした方が良いそうです。
○「低血圧の人は寝起きが悪い」(ウソ)
実は、寝起きの良し悪しは睡眠の質と起きるタイミングが関係するというのです。
まず寝起きを悪くする質の悪い睡眠とは脳が十分に休まらない眠りのこと。
疲れがとれないためすっきりと目覚めにくくなります。
その要因となるのが夜更かしやストレス、深酒など。
また、起きるタイミングも寝起きの良し悪しを左右します。
人の眠りは基本的に深い眠りと浅い眠りをほぼ90分周期で繰り返します。
寝てから6時間後など眠りが浅い時に起きると脳が覚醒状態に近いため寝起きが良く、逆に深い眠りの時に起きると脳が休んでいるためボーッとしてしまい寝起きが良くありません。
こうした寝起きの良し悪しを左右するメカニズムに血圧は関係しないというのです。
○「冷え性対策には靴下を履いて寝るとよい」(ウソ)
冷え性の大きな原因は血行の悪さからくる手先や足先の冷え。
温かい血が巡ってこないため冷えてしまいます。
実は、靴下を履いて寝るとゴムの締めつけにより足先の血行が悪化し、血液が来にくくなり足が温まらなくなることがあるのです。
つまり締めつけるような靴下を履いて寝るのは逆効果になりかねないのです。
●テーマ『動物』
○「ピラニアは人を襲う」(ウソ)
ピラニアは小魚や小動物を食べる肉食ですが実は非常に臆病な性格。
人間など大型の動物が水に入ってくると怖がって逃げてしまうんです。
そのためピラニアが人を襲うことはないのだとか。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
そのきっかけはある1本の映画にあったと言われています。
それは1953年に制作されたドキュメンタリー映画「緑の魔境」。
カンヌ国際映画祭で探検映画賞にも選ばれた名作です。
この映画の中に、牛たちをアマゾン川の対岸へと無事渡らせるために、傷つけて弱らせた1頭の牛を犠牲にするというシーンがあり、どこからともなく現れたピラニアたちが弱った牛を襲い始め、あっという間に骨だけにしてしまったのです。
実は、ピラニアは大きな動物でも弱って血を流している場合にはこのようにエサとみなすこともあるのだとか。
この大きな牛が食べつくされる映像が世に広まり、ピラニアは生きている人も襲うというイメージが生まれたと考えられているのです。
○「ネズミはチーズが好物」(ウソ)
様々なものを口にするネズミですが実はその好物は種や穀物。
他に何もなければチーズを食べることもありますが、全くもって好物ではないのだとか。
◇では、なぜこんな俗説が広まったのでしょうか?
実はその秘密はヨーロッパで人気のエメンタールチーズ(穴あきチーズ)にありました。
倉庫に貯蔵されたこのチーズのかたまりを切ると気泡でできた穴が空いているのですが、チーズに関する知識の乏しかった時代、倉庫に住みついたネズミがかじってあけた穴だと勘違いされ、ネズミはチーズが好きだと信じられるようになったのだとか。
そして、世界的に大ヒットしたアニメ「トムとジェリー」の中で、ネズミのジェリーが美味しそうにチーズを食べるシーンが頻繁に描かれたことでネズミはチーズが好きというイメージが広く根付いたと考えられているのです。
○「シロサイとクロサイ違いは体の色」(ウソ)
実はシロサイとクロサイは体の色ではなく口の形が違うのです。
クロサイの口はやや尖った形をしているのに対し、シロサイは平べったく幅が広い口。
その昔アフリカでシロサイを見た動物研究科が現地の人に「あれは何だ?」と聞いたところ、口が平らで広いので現地の人は「ワイド(WIDE)」と答えたのですが、それを「ホワイト(WHITE)と聞き間違え、以来シロサイという名前になったのだとか。
そしてこのシロサイと分かりやすく区別するためにもう一種のサイをブラック(BLACK)つまりクロサイと名付けたということなんだそうです。
○「ネコ科のライオンやトラもマタタビに酔う」(ホント)
マタタビにはマタタビラクトンという成分があるのですが、なぜかネコ科の動物だけがそのマタタビラクトンに強い反応を示し、人がお酒に酔ったような状態になるのだそうです。
●『ネット情報のウソを見破れ! ネットバスター!』
○File1 【NEWSの語源】
「NEWSとは東西南北の頭文字をとった言葉」(ウソ)
フランス語には新しいという意味の単語「nouvelle」があります。
フランス人は新しい情報に対し、これに「s」をつけた単語「nouvelles」を用いました。
それが14世紀頃、イギリスの王室で真似られ、英語の「NEW」に「S」をつけ、新しい情報を「NEWS」と呼ぶようになったといわれています。
そこから世間の出来事を「NEWS」と呼ぶようになっていったそうです。
○File2 【地下鉄にカーブが多い理由】
「地下鉄にカーブが多いのは運転士の居眠り防止のため」(ウソ)
地下鉄にカーブが多いのは道路の下を通るため。
実は、人の土地の下を掘ると土地代の一部を支払わなくてはならないため膨大な費用が掛かってしまいます。
そこで許可を得るだけでよい公共の道路の下にコースを作るようにしているのです。
だから地下鉄はまっすぐ線路が作れずカーブが多いというわけなのです。
○File3 【セメダインの名前の由来】
「セメダインの名は『攻め出せ!メンダイン』の略」(ホント)
今から90年前、後のセメダイン社の創業者・今村善次郎氏は日本初の接着剤を開発しました。
その頃、接着剤の市場を独占していたのはイギリスの「メンダイン」。
そこで今村氏は市場から「攻め出せ!メンダイン」という思いを込め、それを略して商品名を「セメダイン」にしたといいます。
しかもこのセメダインという名前は英語で語呂合わせすると力強い結合という意味にもなるため、この名前に決めたんだそうです。
そして開発から20年後、セメダインは見事、メンダインの売り上げを抜いたそうです。
○File4 【サケとシャケの違い】
「加工前はサケ、加工した後はシャケ」(ウソ)
日本各地の魚の呼び方を調べた文献によると、一般的には「サケ」東京では「シャケ」と記されています。
つまりシャケの呼び名は江戸っ子訛りが世に広まったものだったのです。
○File5 【つまようじにミゾがある理由】
「つまようじのミゾはつまようじを置くためにある」(ウソ)
元々つまようじにミゾはなく頭の部分はささくれていましたが、昭和30年代後半に導入された機械によって頭が滑らかなつまようじを作ることに成功しました。
しかし、ささくれを削る激しい摩擦で頭の部分が黒く焦げてしまいます。
これでは見た目がよくないと悩んでいたとき、わざとミゾをつけてこけしのような形にしようと閃いたそうです。
そこでミゾが2本入るように機械を調整したところ、頭が黒いこけしのようなつまようじが出来上がったといいます。
つまり、つまようじのミゾは見た目をよくする単なるデザインだったのです。
○File6 【干支の猪はホントは豚】
「干支の猪ってホントは豚」(ホント)
中国では豚は子沢山で富の象徴。
縁起が良いので干支に入っているのです。
干支が伝わった頃の古代日本には家畜である豚がいませんでした。
そこで似た動物の猪が抜擢されたというのです。