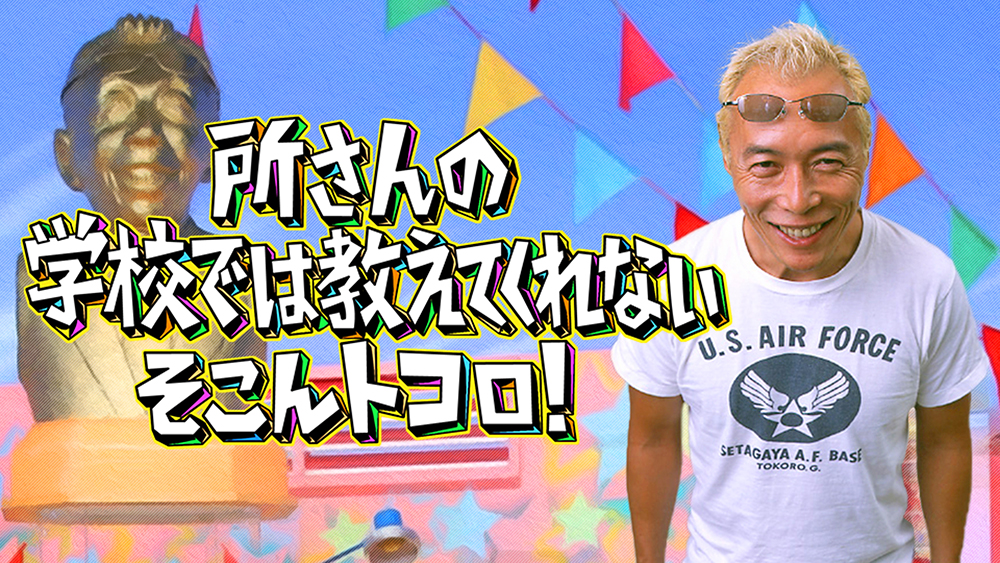『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ!』 テレビ東京 (金) 21:00~
公式HP:http://www.tv-tokyo.co.jp/sokontokoro/
出演者:所ジョージ、清水ミチコ、東貴博、湯浅卓、吉澤ひとみ、大橋未歩(テレビ東京アナウンサー)
●『こんなの見たことねぇ!海のヘンテコ生物』
静岡県三島市「ブルーコーナージャパン」。
◇ブルーコーナージャパン⇒http://www.bluecornerjapan.com/index.shtml
世界160カ国以上の水族館から依頼を受け、様々な海洋生物を提供している会社。
海の手配師の異名を持つ石垣幸二社長にヘンテコ生物を見せてもらうことに。
【ジャイアントメロンシェル】

毒々しい模様の身が殻から大きくはみ出した巨大巻貝。
【ウコンハネガイ】

粘着性のある触手を無数に伸ばし、海中に漂うプランクトンを捕食する。
この貝はイナズマ貝とも呼ばれ、体の一部を震わせて絶えず光を反射している。
ただ何のために光らせているのかはまだ解明されていないという。
【アカシマシラヒゲエビ】
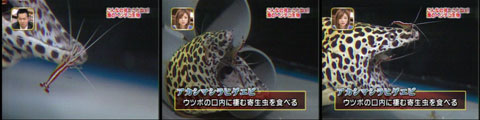
このエビは通称クリーニングエビと呼ばれ、ウツボの口内に棲む寄生虫を食べる。
【タマムシサンゴアマダイ】

一瞬のうちに体の色が変化する魚。
入手が珍しく水族館でも滅多に見ることができないという。
【カエルアンコウ】

ヒレを使って海底を歩く。
●『海のヘンテコ生物捕獲大作戦!』
静岡県伊豆半島の西、戸田漁港。
ここ戸田漁港はタカアシガニやフランス料理に使われる高級食材アカザエビの漁場として知られるが、その漁に同行するとヘンテコな生物に出会えるという。
【ウミケムシ】

全身に毒の毛を持ち敵がくると体を震わせてその毛を撒き散らす危険生物。
【トリカジカ】

細長い体に不釣合いな大きな目。
まるで鳥のような顔つきからトリカジカという名を持つ深海魚。
生きた姿は中々見られない。
【オキナエビ】

深海に生息するザリガニの仲間。
細かい毛に覆われた大きなハサミを持ち、目がほとんど退化している。
【コシオリエビ】

異様に長いハサミを持つコシオリエビ。
常に尻尾の部分が折れ曲がっているところからその名が付いた。
【アカグツ】
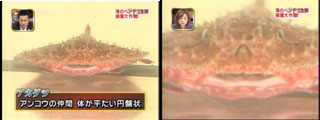
アンコウの仲間。体が平たい円盤状。
【シャチブリ】

頭全体がゼラチン質で半透明の深海魚。
手で触るとプニョプニョの触感。
【メンダコ】

深海300m付近に棲むタコで日本固有の種。
ピコピコと動く耳のようなものはヒレ。
その愛くるしい姿からマニアの間で非常に人気が高い。
しかし飼育が難しく、生きたままの姿はほとんど見ることが出来ない。
そのため詳しい生態はいまだ謎に包まれているという。
●抜き打ちテスト『なぜ紙鍋は燃えないのか?』
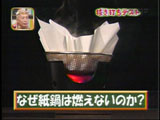
○答え 紙鍋の中に水があるため燃えない
燃えない秘密は紙ではなく、鍋の中の水にある。
水は100度で沸騰し、それ以上温度が上がることはない。
一方、紙の燃える温度は300度以上。
紙鍋に水を入れると紙自体も100度前後の温度にしかならず、そのため紙鍋は燃えないのだ。
●『日本全国漁港巡り 極上の漁師メシを喰らえ!』
◆根岬漁港(岩手県陸前高田市)
所属漁師:約50人
年間水揚げ量:約235トン
ここ根岬漁港は岩手県の一番南、広田半島の先っぽに位置する小さな港。
○『フワフワとろける!極上「どんこ汁」』
まず、ニンジン、大根、タマネギなどの野菜を入れ、どんこの頭を豪快に切り落とす。

これが脂が乗って旨いどんこの肝だ。

身はざっくりブツ切りにし、そのまま鍋へ。
肝を入れたら水を入れ、15分ほど煮込む。

味噌を溶かし込み、最後にネギを投入。
そして碗に盛れば完成!

【漁師メシFILE.0011 根岬漁港どんこ汁】

さらにこのどんこ汁にはとっておきの食べ方が。それがどんこ汁におにぎりを入れた雑炊。
この食べ方は船の上で余計な器を増やさない漁師ならではの知恵なのだ。

●『ミホの甘~い疑問』
◇「にゃあにゃあ饅頭の”にゃあ”の意味は?」
○答え 石川県加賀地方の方言で、若い娘さんのことを”にゃあ”と呼ぶ。
※娘娘(にゃあにゃあ)饅頭 女性が大口を開けなくても食べやすい形にしている。
【今回紹介された和菓子】 石川県「山中石川屋」にゃあにゃあ饅頭

◇山中石川屋⇒http://www.yamanakaishikawaya.com/top.htm