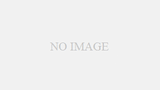『楽しく学べる新教養バラエティ 全国一斉!日本人テスト 祝!2時間30分SP』 フジ 4月3日(木)19:00~21:24
公式HP:http://wwwz.fujitv.co.jp/fujitv/news/pub_2008/n08-006.html
出演者:三宅裕司、MEGUMI、オリエンタルラジオ、オアシズ、片岡鶴太郎、勝俣州和、加藤浩次、KABA.ちゃん、熊田曜子、小林はるか、紺野美沙子、斉藤慶子、佐藤里香、嶋大輔、次長課長、高樹千佳子、高田万由子、つるの剛士、なだぎ武、夏川純、彦摩呂、ますだおかだ、宮川大輔、山田玲奈
●『日本人テスト初級 全8問』
①「立春を過ぎて初めて吹く強い南よりの風を何という?」
◇正解 春一番 (大人正解率99%)
「春一番」は長崎県壱岐の漁師が使っていた言葉で、船を沈めるほどの強風を「春一番」と呼んだ。
②「桜の花びらが風に舞うことを雪に例えて何という?」
◇正解 桜吹雪 (大人正解率76%)
③「富山県の風物詩として知られ、地元では”喜見城(きけんじょう)”とも呼ばれている、光の屈折により風景が伸び上がって見える現象を何という?」
◇正解 蜃気楼(しんきろう) (大人正解率71%)
”蜃(しん)”とは伝説の生き物で巨大なハマグリのこと。昔、蜃気楼はこのハマグリが吐く息によって生まれた幻だと考えられていた。
④「春の水辺で産卵する体調3cmほどの日本最小の淡水魚を何という?」
◇正解 メダカ (大人正解率73%)
目の位置が普通の魚に比べると高いところからメダカと呼ばれるようになった。
⑤「水揚げされた状態の正しいイカの数え方は?」
◇正解 杯(はい) (大人正解率81%)
イカの中身を抜くと胴体が水を入れる容器に見えることに由来する。タコやカニも同様に一杯と数える。
⑥「急所や弱点の例えで用いられる向こうズネのことを”○○○の泣き所”という?」
◇正解 弁慶の泣き所 (大人正解率80%)
弁慶のような強い者でも打たれたら涙を流すということから名付けられた。
向こうズネ以外にも”弁慶の泣き所”と呼ばれる部分があり、それは、足の中指の第一関節から先の部分のことで、指を曲げると力が全く入らないことからそう呼ばれている。
⑦「結婚式で列席者に贈られる品物は?」
◇正解 引き出物 (大人正解率75%)
平安時代の馬を贈る習慣に由来し、馬は庭に引き出してから贈られたため、大切な人への贈り物を「引き出物」と呼ぶようになった。さらに、新たな門出を迎える人への”はなむけの言葉”も馬にちなんだ言葉で、平安時代、道中の安全を祈願して目的地に馬の鼻先を向けた習慣から”はなむけ”という言葉が生まれた。
⑧「童謡『春の小川』の歌詞・”春の小川は さらさらいくよ 岸のすみれや ○○○の花に”の○○○に入る言葉は何?」
◇正解 れんげ (大人正解率70%)
「春の小川」に登場する「れんげ」の正式名は「ゲンゲ」という花。
本来の”レンゲ”は7月頃に咲く蓮花(ハスの花)のこと。
ちなみに食事の時につかう”レンゲ”は蓮の花びらに形が似ている事からそう呼ばれるようになった。
●『日本人テスト特別級 全7問』
①「春にとれる鰹のことを特に何という?」
◇正解 初鰹(はつがつお) (大人正解率67%)
昔から初鰹は縁起物とされ江戸時代には女房を質に入れてでも食えといわれていた。それは初物を食べると七十五日長生きできると考えられていたからである。そのため江戸時代は初鰹1匹の値段が米俵5俵(300kg)と同じだったという。
②「似たような物事が次々と現れることをことわざで”○○○のたけのこ”という?」
◇正解 雨後の筍(うごのたけのこ) (大人正解率36%)
筍は雨が降った後次から次へとはえてくることから。
③「富山県が漁獲量日本一を誇る、危険を感じたときに青白い光を放つ海の生き物は何?」
◇正解 ホタルイカ (大人正解率79%)
富山湾のホタルイカが群生する海面はその美しさから昭和27年に特別天然記念物に指定されている。天然記念物なのはその海面であり、ホタルイカ自体は天然記念物ではないので食べても良い。
④「愛知が収穫量日本一のこの山菜の名前は?」

◇正解 フキノトウ (大人正解率69%)
フキノトウとは野菜のフキの花のことで春に芽吹く蕾(つぼみ)が食用になる。ほろ苦いふきのとうは冬の間になまった味覚を目覚めさせてくれる春の風物詩である。
⑤「”菜の花”の正しい名前は?」
◇正解 アブラナ (大人正解率34%)
種を絞ると油がとれることから菜の花の正式名は油菜(アブラナ)という。
⑥「栃木で生まれ日光の山々にちなんで名がついたこの有名なイチゴの品種は何?」
◇正解 女峰(にょほう) (大人正解率14%)
1985年に栃木県農業試験場で誕生し日光連山にちなんでこの名がついた。断面が美しいことからデコレーションケーキによく用いられる。
⑦「ニシンの卵を何という?」
◇正解 数の子 (大人正解率52%)
その昔、ニシンのことを”カド”、”カドイワシ”と呼んだことから”カドの子”がなまって”カズの子”になった。
●『日本人テスト中級 全7問』
①「三名泉の1つ群馬県にある温泉は?」
◇正解 草津温泉 (大人正解率58%)
「草津」の由来は酸性が強く硫黄の香りが混じった湯の香りから来ている。
「くさい水」という意味の言葉「くそうず」が次第になまり「草津」になったのだそう。
②「”坂東太郎”の別名を持つ流域面積が日本一の川は?」
◇正解 利根川 (大人正解率52%)
坂東とは昔の言葉で関東地方を指し、日本の長男格の川ということで”坂東太郎”と呼ばれることになった。
③「日本最南端の島の名前は?」
◇正解 沖ノ鳥島 (大人正解率50%)
沖ノ鳥島は熱帯気候に属しハワイのホノルルとほぼ同じ経度にある。
④「ご祝儀袋などを包むときに使う布を何という?」
◇正解 袱紗(ふくさ) (大人正解率59%)
昔、贈り物を贈ることは清らかなものであるべきと考えられ、贈答の品を直接手渡しすることはタブーとされた。よって、掛袱紗(かけふくさ)で品物を覆ったり、小袱紗(こぶくさ)で物を包んだりして相手に差し出すという習慣が生まれた。袱紗には使用する場面によってふさわしい色があり、「慶び事」では「エンジ」か「赤」系統を、弔事では「紺」「グレー」など地味な色を用いる。現在は紫が慶事・弔事共に使えるという認識が広まっている。
⑤「”花祭り”が行われる4月8日は誰の誕生日?」
◇正解 お釈迦様 (大人正解率54%)
お釈迦様が美しい花園で生まれ、そのとき龍が甘露(かんろ)の雨を降らせたという伝説から現在でも花を飾り甘茶を注ぐ。
ちなみに、物が壊れたり何かがダメになってしまうことを「おシャカになる」というが、これは元々は江戸の鋳物職人から生まれた隠語(業界用語)で、鋳物がダメになる原因の「火が強かった」が江戸っ子なまりで「しがつよかった」⇒「4月8日」で、お釈迦様の誕生日にかけて「おシャカになる」というようになった。
⑥「数え年で99歳のお祝いを何という?」
◇正解 白寿 (大人正解率51%)
”99”は”100-1”であり、漢字の”百”から”一”を引くと”白”という字になることから白寿となった。
このような数え方はさらに続き、100歳を百寿(ひゃくじゅ)250歳を天寿(てんじゅ)と呼ぶ。実際250歳まで生きる人はいないが「天寿を全うする」という言葉はここから来ている。
⑦「桃太郎が持っている”のぼり”に書かれている文字は?」
◇正解 日本一 (大人正解率50%)
元々は「日本一のきびだんご」と語られていたものが、絵で表現されるようになると”日本一”はのぼりに書かれるようになった。
ちなみに桃太郎は、桃から生まれたというのが今の常識だが、明治初期までは桃を食べて若返ったおじいさんとおばあさんの間に桃太郎が生まれたというお話だった。
●『日本人テスト特別級 全9問』
○テーマ 「日本のマナー」 ☆2択問題
【初級の階】
①「普段お世話になっている友人の家に手みやげを持って訪れました。このとき、おみやげを渡すタイミングとして正しいのは?」
(A)玄関先
(B)部屋の中
◇正解 (B)
おみやげは部屋に通されて正式にあいさつをした直後に渡すのがマナーとされる。このとき紙袋などに入れて持ってきた場合は袋から出して渡す。
ただし、物によっては玄関先で渡した方がよい場合もあり、例えばアイスクリームなどすぐに冷蔵庫に入れて欲しいものや、すぐに目に入ってしまう花束なども玄関で渡した方がよい。
②「お通夜に持っていくべき香典袋は?」
(A)袋の文字が「御仏前」
(B)袋の文字が「御霊前」
◇正解 (B)
「御仏前」は仏式の法要で四十九日以降に使うもので、お通夜に持っていくものではない。
多くの仏教では四十九日前はまだ成仏する前なので「霊」が正しい。
③「お祝いの贈りもので”お返し”が必要なのは?」
(A)出産祝い
(B)入学祝い
◇正解 (A)
出産祝いのお返しは内祝いとして返し、生まれてから1ヵ月後に行う「お宮参り」の日かその前後に返すのがマナー。お祝いを頂いたおかげで無事に成長できそうですという意味を込めて子供の名前で返す。
一方、入学祝いはごく身内のことであり、お互い様なのでお返しは不要。ただし、頂いたらすぐに電話や手紙で子供からお礼を言うようにさせる。
【中級の階】
①「女性が手紙を書くとき”拝啓”で始まる文章の終わりとしてふさわしいのは?」
(A)敬具
(B)かしこ
◇正解 (B)
「頭語」や「結語」は元々男性が使用した言葉で、女性が使うのは生意気だとされ、女性の手紙は「かしこ」で終わるのがよいとされた。「かしこ」とは「かしこまって」「ちゃんとかしこまって」という意味である。
ちなみに、前略で始まる文章には男性の場合は「早々」、女子の場合は「あらあらかしこ」という言葉を使う。「あらあら」とは「あらい」の「あら」、つまり「あらあらしい簡単な文章で失礼します」という意味である。
②「食事中に一旦箸を休ませたくなったとき、もし箸置きがなかったら…マナーとしてふさわしいのは?」
(A)器の上にきれいに並べておく
(B)箸袋を箸置きの代わりに使う
◇正解 (B)
お箸は一緒に食事をしている人に箸先が見えないようにして置くのがマナー。箸袋もない場合はなるべく低いお皿に先をかけるのがマナー。
③「急遽入院した上司のお見舞いに行くことに…持って行くものとしてふさわしいのは?」
(A)現金
(B)フルーツバスケット
◇正解 (A)
入院中は食べてはいけないものが多いので必ず相手に確認をとってから持って行くべきである。
目上の人に現金を渡すのは失礼とされていたが今はそんなことはなく、何を持っていくべきか分からない場合は現金や商品券などが間違いがなく最も喜ばれる。
【上級の階】
①「結納の席に出すのにふさわしいのは?」
(A)緑茶
(B)昆布茶
◇正解 (B)
緑茶は仏教と深い関わりがあり、葬儀や法事などの引き出物として使われることが多いため、おめでたい席では敬遠される。
一方、昆布茶は”子生茶”⇒”子を生む茶”となり縁起がよいとされている。
②「親戚の家にお邪魔したときお茶とお茶菓子をいただきました。お茶とお茶菓子をいただくときマナーとして正しいのは?」
(A)お茶からいただく
(B)お茶菓子からいただく
◇正解 (A)
茶道の場合はお茶菓子が先だが、これはお茶の粉そのものをいただくため味が濃く胃に少し強いため。
普段飲む煎茶はこれとは違い、入れるお湯の温度をちょうど「うまみ」と「甘味」が出るようにしているものなので、出してもらったらまずひと口いただくのが礼儀である。
③「手紙の入れ方として正しいのは封筒の表から見てどちらが正しいか?」
(A)便箋の右側が前
(B)便箋の左側が前
◇正解 (A)
昔、手紙が「巻き紙」だったとき右側から書き、左から巻きあげたことに由来している。
ちなみに、「訃報」や「法事のお知らせ」など悲しみごとの場合は逆になり左が前になる。
●『日本人テスト上級 全6問』
①「春に雨の日が続くことを”○○○梅雨”という?」
◇正解 菜種梅雨(なたねづゆ) (大人正解率25%)
②「傾斜地にある階段状の田んぼを何という?」
◇正解 棚田(たなだ) (大人正解率29%)
大量の雨が降った場合、傾斜地では土砂崩れが心配だが、棚田は水を蓄えるダムの役割を果たすため、そのような災害も未然に防いでくれる。
③「”枚””通”以外のハガキの数え方は?」
◇正解 葉(よう) (大人正解率22%)
例えば、母親からもらった励ましの言葉が書かれたハガキや、友人からもらった熱いメッセージの書かれたハガキなど特別な思い入れがあるハガキを葉(よう)と数える。
手のひらにのせ「葉」のように眺めていたいという想いからそう数えられるようになった。
また思い入れのある写真も「葉」と数える。
④「”神様”の正しい数え方は?」
◇正解 柱(はしら) (大人正解率14%)
古くから日本では柱をたてて神様を祀ることで、柱は神様が宿る場所として考えられていた。そのため神様を柱と数えるようになった。また同様の考え方から霊魂や魂も柱と数える。
⑤「黒い招き猫にはどんな意味がこめられている?」
◇正解 厄除け (大人正解率11%)
黒猫は不気味なイメージを抱きがちだが、一方で神秘的で魔除けの力があるとされている。
⑥「特別な日を指す言葉”ハレ”に対して普段の生活を何という?」
◇正解 「ケ」 (大人正解率15%)
戦前までは普段着を「ケ着」というなど「ケ」が使われていた。しかし、生活が豊かになり毎日でもお酒が飲める現代では「ハレ」と「ケ」の区別が薄まり言葉自体も使われなくなった。
●『日本人テスト超上級 全4問』
①「水面に散った花びらが重なり流れる様子を”花○○○”という?」
◇正解 花筏(はないかだ) (大人正解率8%)
水を流れる花びらが筏のように見えることから名付けられた。
②「山の正しい数え方は?」
◇正解 座(ざ) (大人正解率4%)
山が人間のどっしりと座っている形に似ている事から例えられた数え方。
この他に入道雲も座と数える。
③「ちらし寿司の具の4色(青、赤、白、黒)が持つ重要な意味は?」

◇正解 四季 (大人正解率3%)
昔から日本では太陽の動きから連想して四季を色で表現する風習があった。
”青”は太陽が東から昇るさわやかな様子を表した色、つまり青春という言葉があるように”春”を指す。
”赤”は太陽が真上に来る南中なので気温が高い様子を表した色、つまり”夏”を指す。
”白”は太陽が西へ沈む様子を表した色、つまり”秋”を指す。
”黒”は太陽が沈み真裏にきて真っ暗になる様子を表した色、つまり”冬”を指す。
また、ちらし寿司の上にそれぞれ四季を意味する4色の具と、錦糸卵など「太陽」を意味する黄色の具を乗せることで宇宙全体をいただくという意味がある。
④「仏壇でよく見かけるこの仏具の名前は?」

◇正解 りん (大人正解率6%)
この「りん」はたたくことで仏様に呼びかけるための道具である。
『楽しく学べる新教養バラエティ 全国一斉!日本人テスト 祝!2時間30分SP』